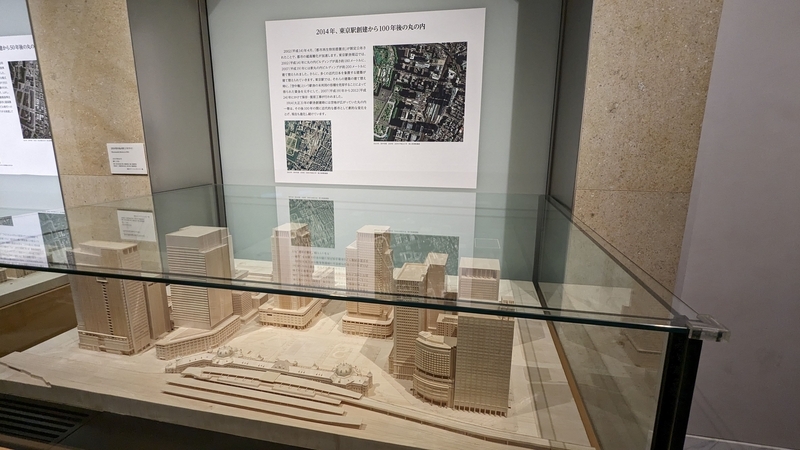なんだかユーウツなときは散歩が一番。
と言いつつインドア派な島鉄です。
散歩のススメ

皆さんは、登山にスキューバダイビング、スキー・スケートお手の物、しまいにゃハンググライダー。
なんてフットワークの軽いアウトドア派ですか?

それとも、どちらかというと家にいて映画見たり、読書したり、漫画読んだり、絵を描いたり、ブログ記事書いたり(たまに琵琶湖を一周する)……なインドア派ですか?
上記インドア派に該当する人は島鉄とほぼ行動が被っているので今度お茶しましょう!
さて、ここまでつらつら書いてきたのは、なにもアウトドア派・インドア派論争がやりたかったからではありません。
自他ともに認めるインドア派な島鉄も、たまには外に出たくなる時があるのです。
「このまま1日家にいるとおかしくなりそうだな〜」
と思って外に出ます。特に行先はありません。
東西南北どちらへ行こうかな、くらいの考えです。
前置きが長くなりました。
伝えたいことは「島鉄が唐突に外出する癖の持ち主で、これから皆さんに散歩のススメをする」ということ。
ある日の昼下がり、ブラブラ散歩した記録を記事にしてみました。たまには(わりと、かもしれません)行き当たりばったりもいいじゃない。
ソイツは旧twitter(X)に流れてきた
その日はなんの予定もいれずに、のんびり過ごしていました。
1時間近く洗濯機の水栓から水が出ずに格闘していたり、コーヒー豆を挽いて、その間すっかり冷めたヤカンの水を再び沸かしたり……。
贅沢な時間の使い方。休日とはかくあるべきでしょう。休みの日もスケジュールギチギチな人はスゴいと思いますが、とても真似できません。
休みの日くらいは、カレンダーも時計も見たくないです。
そんなとき、ぼんやり眺めていたtwitterにとあるツイートが流れてきました。
昔のマニア系TVの軽薄なナレーション好きです pic.twitter.com/v3choFDLIe
— NyangTang / にゃんたん (@ohmyasshole) 2024年4月11日
このツイート内の動画によると、板橋区は本蓮沼の中山道沿いに昔懐かしいマニア垂涎のファミコンショップがあるのだとか。
これは行くっきゃない!
ファミコンショップが取り上げられたTV番組は2000年放送ともうすぐ四半世紀前(2024年現在)、検索すると10年前のレビューが最新……なんか潰れてそうですが気にせず都営地下鉄三田線へ乗り込み、本蓮沼駅へ向かいました。

ちなみに島鉄は一度も本蓮沼に行ったことがありません。ドキドキしますね。
初めての本蓮沼へ

さて本蓮沼駅に面した大通りは、前述の通り歴史のある街道……中山道です。
熊野古道や奥の細道と並んで知られた古道、中山道は江戸時代に整備された五街道の一つで、江戸と京都を内陸で結びます。
長野県に縁のあった島鉄的には木曽路が有名な中山道ですが、まさか板橋でその名を目にするとは……。

高速道路の高架*1が見えてきます。動画で見たとおりの風景です。

住民へのマナー喚起のゴミ捨てアナウンスが過剰でツボです。
どれだけ言葉を尽くしても伝わらないことってありますよね。
本蓮沼、なかなかポテンシャルが高い街かもしれない。

中山道と高速道路は並走しています。この並走区間に件の「ファミコンショップ クラブハウス」があるとのことなのですが……。
全然見当たりません!!
もしかして、やっぱり……閉店していたのでしょーか??
番組ナレーションで触れられていたあの宝の山*2はいずこへ……。
HPもなくなっていました。悲しい……。
http://www3.cnet-ta.ne.jp/o/ogclub/
(↑↑動画に出てきたURLをベタ打ちしたもの。アドレスを読んで入力するのは、かなり久しぶりの感覚です……。)

昔からやっていそうな店もいちおー発見したのですが、隣は無慈悲にも開発中……。
とゆーか、この再開発中の土地が探し求めているファミコンショップなのでは?!

Timesの駐車場があり、ファミコンショップは確実にない気配ですね。
うーむ……悲しい。


道路の反対側に回って探してみよう、と思い立ち中山道を渡りました。
首都高の下に謎の空間がありますね。歩いていくと、その果てにはへし曲ったガードレールが特徴の広場ともいえない空間があります。

ここ、公園なのかな……?
ゼンリンの地図にも名称の載っていない空間で、公園によくある水道の蛇口をひねったら水が出ました。
……当たり前。この水、結構勢いが強くて服が濡れました。気をつけてください。
名もない公園*4を発見できてよかった。
ファミコンショップ探しはこれにて断念します。


この虚無公園のある高速下を脱して中山道沿いに進むと、パイクを置き過ぎではないのか、と不安になるバイクショップと北海道札幌発祥のどさんこラーメン、そして沖縄ショップ(飲食店)が表れます。
歩いて2分くらいのところに北海道と沖縄がある……本蓮沼のスケールの大きさが伺えますね。どさんこラーメンは営業してなさそうですが。

ちなみに沖縄ショップのバイト募集要項は18歳-70歳ぐらいまで、と幅広い年齢層の応募を許す懐の深さ。ただここも、どさんこラーメンと同じく空いていませんでした……。

駅前まで戻ってきて家系ラーメンの「ライス無料」の圧力に頬が緩んだり

昔ながらの看板建築を発見して思いを馳せたり
そんな時間を過ごして島鉄は帰路につこうとしていました。
しかし、地下鉄の駅に入る前に「アスリート通り」なる看板が目に入ってきて足が止まります。
アスリート通りと商店街、団地

蓮沼のあらゆるアスリートが煮込まれている……失礼ながらそんな第一印象を受けた島鉄はこの通りを歩かないわけにはいかない!
と思い立ったのです。


角のタバコ屋に、クリーニング屋、精肉店……駅前のマンションがニョキニョキ建っている風情とは真逆の商店街がアスリート通りには広がっていました。


そんなノスタルジーな島鉄の気を引いたのは「酸素カプセルのお店」です。微妙な懐かしさ。
流行に全部のっかっていくスタイル*5の店頭画像ペタペタも個人的には好きです。
酸素カプセルの効能についてもペタペタ貼り付けられていました。
安いのか高いのか相場観が分からないので謎ですが4,000円台で施術してくれるそうです。
フフフ……アスリート通り、名前のわりにアスリート要素が酸素カプセルくらいだな、なんて思いながら歩いていると綺麗な桜並木と遭遇。
満開の桜には目を惹かれますね。

そしてこの桜並木のすぐそばには、アスリート通りの由来となったナショナルトレーニングセンターや国立スポーツ科学センターなどの施設が建ちならんでいます。
綺麗な桜も嬉しいですが、島鉄的に嬉しいのは、何と言っても団地があること!

低層だけど、しっかり後付のエレベーターがある団地です。
私の住んでいた団地、宿舎にはエレベーターがなかったので羨ましい。

TOPPANの大きな社宅(?)もありました。
ニュースで見たけど、ここだったのかな。
ピカピカの社宅もすきですが、島鉄的にはこの団地のよーわからん動物さんがすきです。

頭陥没アニマル、かわい~。
再開発真っただ中、カフェに行く

団地と住宅、印刷工場の並ぶ地域をフラフラ歩いていると元いた地下鉄の駅近くまで戻ってきました。
折角なのでどこか店に入りたいな……と思って辺りを見渡すと、現実に引き戻される「境界あります」の文字……。
本蓮沼も再開発でバチバチしているのだなあ、と遠い目をしていると比較的新しい喫茶店が目に入りました。

店名にどーゆー店なのか情報を全部載せしていらっしゃいます!
なかなか素敵な雰囲気を纏っていたので即入店しました。
アロマディフューザーのおかげか、店内はリラックスできるシトラス系の香りに包まれており、ボサ・ノヴァの流れる落ち着いたお店です。
マスターは短髪のおじさま。

産地にこだわりのあるメニューがずらり。
コロンビアとチーズケーキを注文。ちなみに飲み物とセットで注文するとフード類は200円引きだそうです。

チーズケーキは固くしっとりとした味わい。
コロンビアは酸味が強めで、チーズケーキの味を邪魔しない(が口の中をリセットしてくれる)。
マスター曰く、去年(2023年)の9月からお店を始めたそうで、元はバーだったのだとか。なるほど内装も縦長でカウンターの椅子はたしかにバーっぽいですね。
お会計の時にアーモンド菓子がもらえるのも高ポイント。みなさん2、3個取られますよとのことでした。嬉しいですね。

古い建物と新しいマンションが混在する不思議空間、本蓮沼。しばらくしたら再開発でその面影も見えなくなるかもしれません……。
いつまでもあると思うな街の雰囲気。
気になったら即行動、これだいじ。
思い立って散歩するのも案外悪くないものですね。
肝心のファミコンショップには寄れませんでしたが、なかなか楽しい散歩ができた島鉄でした。
皆さんも、レッツ衝動散歩!